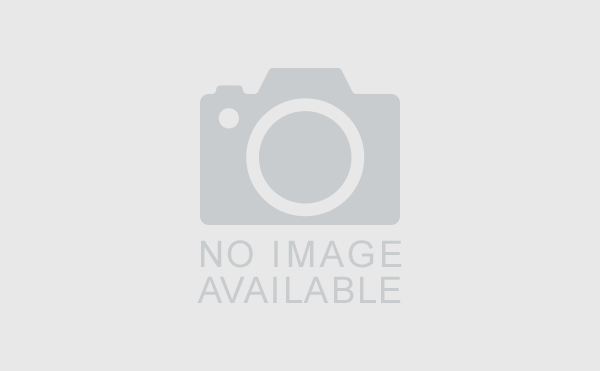徳島生物学会で「世界農業遺産」の基調講演
2025年1月11日、徳島大学で開催された徳島生物学会で環境人類学博士の林博章氏は、記念すべき基調講演を行った。そこで忌部研究より始まった剣山系の伝統農業の特徴を、スライドを交えながら45分間講演した。会場には生物学会理事で忌部文化研究所の顧問を務める浅川義範教授も同席した。その内容は次の通り。
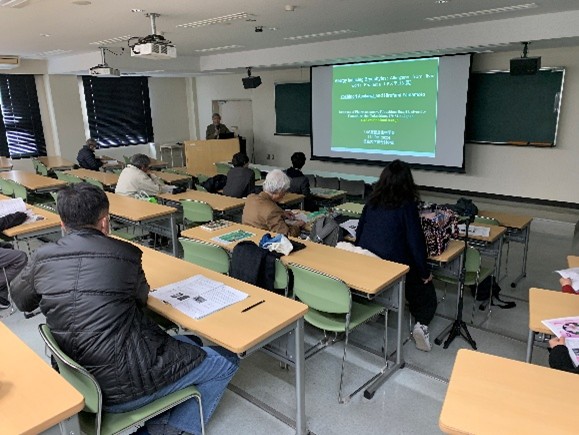
徳島剣山系の世界農業遺産~持続可能な社会への道標~ 環境人類学博士 林 博章
1. はじめに
2018年3月に「にし阿波の傾斜地農耕システム」は、国連食糧農業機関(FAO)の世界農業遺産(GIAHS)に登録された。私は、日本各地に農文化を伝播させた剣山系を拠点とする忌部氏の古代史研究を深化させるなかで、日本に前例のない剣山系の特徴的な農文化は世界的に評価されるべきものと確信した。そこで剣山系の農文化やその風景を世界農業遺産に認定させようと、剣山系に展開される伝統農業、農文化、産業、地質、植生などの総合的な調査を実施して原案を作成、写真展や講演活動などの運動を展開していった。その動きは行政を動かす原動力となり、それが徳島大学、農林水産省をまき込むまでとなり、徳島県初の世界遺産が誕生した。その原案や基礎資料は、2015年に「剣山系の世界的農業文化遺産」で発表した。その論考は海外学者の目に留まり、2022年11月にIOUF(異文化間オープン大学財団・アメリカ)より環境人類学、国際的に連携するアステカ大学(メキシコ)より環境学の博士号(Ph.D)を取得するに至った。
2.傾斜地農業の成立と焼畑農業と遺伝資源
・徳島平野を東流する吉野川南岸部より剣山系にかけた地域、[三波川帯][御荷鉾帯]の結晶片岩地域に剣山系の伝統農業(傾斜地農業)は展開する。地質面から検討すれば、「剣山系の結晶片岩帯で展開される傾斜地農業」とも捉えられる。その結晶片岩の性質が、農業や景観の多様性を育む要素となった。当地域は、日本を代表する地すべり地帯で、しかも日本最大の破砕帯が走っているため、山上部に容易に畑地・棚田・集落を作ることができ、涵養林さえ残せば山上付近からでも水が湧き出るため、土地生産性が高く、古代より農業生産の場として機能してきた。それ故に、日本に前例がない標高差最大400mを越える日本最大の傾斜地集落と独特な農村景観が歴史的に形成されてきた。

吉野川下流部の人々は、この傾斜地集落を「ソラ」と呼称した。「ソラ」が分布する剣山系は、かつて日本を代表する焼畑農業地帯であった。現在でも、焼畑農業を継承するアワ・シコクビエ・ヒエ・アズキ・ダイズ・ソバ・コキビ・タカキビ・トウモロコシ・コンニャクや、貴重な在来種(太きゅうり・ゴウシュイモ)など、多種多様な農作物が栽培されている。剣山系は日本を代表する作物遺伝資源の宝庫(ジーン・バンク)なのである。

雑穀の生育特性による系統分類では、コキビ19系統、アワは3系統、タカキビ6系統、ヒエは祖谷系とシコクビエの1系統が確認されている。国立研究開発法人「農業・食品産業技術総合機構」のジーンバンクでは、徳島県雑穀類65系統が保存されている(ソバ11、キビ16、ヒエ5、シコクビエ13、アワ19)。また、貴重な在来種の種が各農家で保存されている実情は見逃せない。2021年には、祖谷の在来雑穀の6種類、シコクビエ、ヒエ、アワ、コキビ、モロコシ(タカキビ)、ソバが食の世界遺産「食の箱舟」に登録されるに至った。
3.剣山系の傾斜地農業の特徴
・剣山系の伝統農業の最大の特徴は、険しいV字型渓谷の山間部の傾斜面で農業を営んでいることであり、その傾斜は最大で30度を超える。剣山系では、水捌けを良くするため、農地は平坦(フラット)にせず、傾斜をそのまま利用して 農作物が栽培される。結晶片岩の土壌は多孔質で、傾斜があれば、水捌けが良好で、根が深く入り、多種多様な農作物を栽培する最適地であった。この傾斜地で傾斜地農業を持続的に営むには、土壌流出を防ぐ高度な知恵と技術が肝要で、一応にカヤを施用する農文化が見られる。それは、伝統的にカヤ場(肥場・肥野・肥山)と呼ぶ採草地を確保し、秋にカヤ刈りを行い、伝統農業のシンボルと位置付けられる[コエグロ]を作ることで保存し、そのカヤを春に傾斜畑に投入し、土壌流出を防止する。

剣山系では、農地と肥料となるカヤ場(採草地)が共存する風景が形成されている。即ち、農業における自然循環の考え方が広範囲に現在でも生き続けているのである。傾斜畑にカヤを敷く意味と効果は、土壌流失だけではない。他に持続的な施肥効果、雑草防止、保水力・保温力、ミミズ・小虫・生物などの養成、生物多様性の保全など多岐に渡る。カヤの施用技術についても、切カヤを使用する方法、表層堆肥にする方法等と様々で育苗にも利用される。このように、昔ながらの自然循環の思想とあわせ、カヤ場(採草地)の管理・維持・利用こそが、持続的な傾斜地農業を成立させる要件なのである。以上のような長年の経験と勘で培われた伝統技術と知恵をもって、持続的な傾斜地農業と傾斜地集落の存続を可能としたのである。また、カヤ場こそは、薬草・山菜・山野草・昆虫類など多様な生物の宝庫であった。「四国自然史科学研究センター」の調査(2015)によれば、カヤ場には、282種の植物が報告され、中にはレッドデータブックに掲載されるシコクフクジュソウ・フナバラソウが含まれている。カヤ場の維持により、絶滅危惧植物を含む多くの動植物が保全されているのである。(「世界農業遺産認定申請書」より)

・さらに、傾斜地集落の機能を概観すれば、約100~700m内に形成された集落は、森林に周囲を囲まれ、そのことが風害、水害、霜害、傾斜地集落の崩壊を防いでいる。民家は農業に不適な場所に建て、適所にカヤ場(採草地)を配置し、地勢に合わせ結晶片岩の石垣を効果的に積み、適所で農地の有効的配置を行い、要所に巨樹・巨木・社叢林・森を残し、自然への畏敬、感謝などの宗教的心情をもちつつ傾斜地農業を営んでいる。共同体意識を醸成する存在として要所に「御堂」が置かれている。剣山系では、民家、採草地、畑地、棚田、果樹地、社叢、お堂、神社などが一体感をなし、独特な豊かさを感じる農村景観がパノラマ的に構成されているのである。

・剣山系の傾斜地集落は、いつ頃より形成され始めたのか。それは、断片的な資料からの検証だが、縄文後期頃の約3000年前、原始的な焼畑農耕の時代に遡ると考えられる。剣山系では、傾斜地の土壌流出を防ぐために、主にカヤを施用しながら多種多様な知恵・工夫・技術を凝らし、その上で傾斜地の特性(風土)を最大限に生かし、標高、傾斜度、日照量、気候、地勢、地質に応じ作物を栽培し、適地適作農業を営んでいるのが、剣山系における傾斜地農業の最大の特徴であり、傾斜地集落そのものが持続可能な農業知識・技術の集合体なのである。これら農業技術や知恵は、世界各地に技術移転することが可能であり、その思想は持続可能な社会の実現という地球社会の命題に大きな示唆を与えることになるだろう。